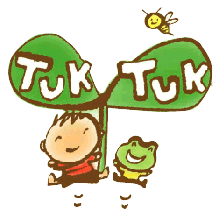越冬準備については先日書きましたが、実際、今年私が行っているベランダビオトープの越冬準備について書いておこうと思います。
基本的な越冬準備についてはコチラ
-

-
ベランダビオトープ、メダカの為の越冬準備
ベランダビオトープも、もうすぐ冬を迎えます。 夏はあんなに忙しかったメダカの世話ですが、冬になると、ほとんどやることはなくなります。 秋は、安全にメダカを越冬させるための準備期間。 来年の春、何匹生還 ...
続きを見る
-

-
【越冬準備】メダカの冬越し、まずは何から?メダカは濾過なしで何匹入れられる?
我が家のメダカも5回目の冬を迎えます。 今、悩んでいること、それは冬越しのときに、どのメダカをどの容器に入れるか、です。 よく言われるのが、濾過なしだと、メダカ親魚は3リットルで1匹。・・・となるとで ...
続きを見る
東側のベランダは寒い
今までは南側に睡蓮鉢を置いていたのですが、日中は20度以上にまで上がり、夜間は10度以下まで下がるという、毎日15℃ほど水温が変わる、極端に寒暖差のある場所だったため、今年の春から東側に移動させました。
その環境でも全滅することなく、毎年、ミナミヌマエビ、メダカ共に生還はしてくれていたのですが、どちらがいいかなあと思いながら東側で初越冬チャレンジ。
日当たりの良い南側と違い、午前中の数時間だけ日があたり、あとは日陰なので、ほとんど水温が上がりません。
更に強烈な風が吹くので、10月のまだ暖かい日でも、気化熱によりすでに水温が15℃を下回っていました。15℃を切るとメダカの活性は目に見えて下がって、餌食いも悪くなります。まだまだ餌をしっかり食べて太って欲しい時期なのにこれはまずい、と思い、本気で保温対策に乗り出すことにしたのです。
睡蓮鉢の保温

大きい方の丸い睡蓮鉢は、もともとが発泡スチロールで保温性が高いので、鉢自身には保温対策は行いません。
気温よりも水温の方が低かったことから、強風により気化熱で水温が下がっていると考えられるので、蓋をすることにしました。
といっても、直径が70㎝超のためいい蓋が見つからず、100均の発泡スチロールボードを浮かべてみることに。
まずは試しに半分だけ、発泡スチロールボードを浮かべてみたところ、効果てきめん。気温以下に水温が下がらなくなりました。そして昼夜の寒暖差も2~3度。なかなかいい感じ。
寒くなってきた今は、写真のように夜は2枚浮かべています。
手前のプラ舟の方は、ウォーターコインが飛び出していたので、1枚だけ発泡スチロールボードを浮かべ、100均で買ってきた網に梱包用のラップを巻き付けて蓋にしています。蓋をしないと風で飛んでいっちゃうんです。
朝になると発泡ボードを外し、蓋だけにしています。

今朝の大阪の最低気温は11℃、水温は13.8℃でした。
泳ぎはゆるやかですが、まだ餌をねだりに来ています。日中どれだけ気温が稼げているかなあ。
さらに寒くなる前に

ちょうど余っていたので、プラ舟の方は、同じものを重ねて二重にする計画です。2つのプラ舟の間に、包装用のフワっとしているシートを断熱材がわりにはさんでみます。
今はウォーターコインを気遣い、半分しか蓋をしていませんが、そろそろもう1周り大きい蓋を全面にかぶせる予定です。ごめんねウォーターコイン。
睡蓮鉢の方は、発泡スチロールボードの浮かべる蓋だけでなく、ラップ蓋もあわせて導入予定です。
まとめ
これで無事、冬を乗り越えられるでしょうか。毎年、秋はドキドキです。
例年はミズトクサのせいで蓋が出来ず、寒い冬を過ごさせてしまっていましたが、今年はミズトクサ撤去により、ビニールハウス状態を作り出すことが出来そうです。ベランダビオトープは高さがある草を植えていることが多いので、蓋が出来ないところがつらいところですよね。寒い日だけでも発泡スチロールボードをうまく活用して保温したいものです。
みんな春までがんばれ!!
2019年はついにビニールハウスに手を出しました。
-

-
メダカの越冬対策、今年は簡易ビニールハウスを作ってみた
表題通り。ついに今年は、ビニールハウスを作ってしまいました…。 もう、もはやビオトープでも何でもない、ただの屋外メダカ鉢になりつつある、私のベランダビオトープ(嘘)。 ビオトープとは、やはり本来は自然 ...
続きを見る